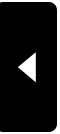2023年06月11日
「中之島蔵屋敷跡を辿り江戸時代、大坂の繁栄を想う」
今週も各種団体を3回歴史街歩きを実施。
江戸時代の大坂は「天下の台所」、蔵屋敷は「天下の台所」の象徴。その蔵屋敷があった中之島を江戸時代の古地図で辿る。
大阪市役所、美作の国津山藩があったところで、江戸時代の古地図で中之島を端から端まで案内を実施しました。
梅雨のさなか、雨にも振られず今年もお天気男の神髄発揮です。





江戸時代の大坂は「天下の台所」、蔵屋敷は「天下の台所」の象徴。その蔵屋敷があった中之島を江戸時代の古地図で辿る。
大阪市役所、美作の国津山藩があったところで、江戸時代の古地図で中之島を端から端まで案内を実施しました。
梅雨のさなか、雨にも振られず今年もお天気男の神髄発揮です。



2023年05月30日
「江戸時代最も愛されしなにわ三橋を巡り中之島周辺の歴史とバラ園を楽しむ」
江戸時代、多くの橋のなかでも最も愛されてきた、天満橋、天神橋、難波橋、なんと大川は今より広く200mを超える大橋。それ故に周辺には歴史と文化が宿る。三橋周辺に残る歴史を感じながら現在愛されしバラを鑑賞するということで先々週から先週は何と何と5組も歴史探訪を実施しました。
グルメ会も、お寿司、鉄板料理、地鶏料理、和食、イタリアンとバライティ豊かに設定しました。参加者は別々なので関係ないのだが私がいくら美味しくても、毎日同じ物を食べるのはたまりませんので。












コースとしては
天満橋→天満橋公園(橋名飾板)→将棊島粗朶水制跡碑→淀川三十石船舟歌碑→天満の子守歌碑→天満青物市場碑→フジハラビル天満堀川跡→吹小屋町筋→蔵のまち天満・菅原町→難波橋→中之島公園→ばらぞの橋→ラジオ塔→天神橋→渡辺津→八軒家浜→天満橋
いつもの私のパターン、古地図と、現在の地図と照らし合わせ、今と昔をイメージして歩いて好評を頂いています。
写真は某カルチャーで2年目で14回目となっていますが、何と女性ばかりの9人の受講生、若い人も多く歴史講座にも関わらず女性に人気があります。
案内は多いグループは35名から最小9名の講座です。
沖本会からシニアの定期講座、カルチャー等の定期講座から単発までにぎやかです。
グルメ会も、お寿司、鉄板料理、地鶏料理、和食、イタリアンとバライティ豊かに設定しました。参加者は別々なので関係ないのだが私がいくら美味しくても、毎日同じ物を食べるのはたまりませんので。


コースとしては
天満橋→天満橋公園(橋名飾板)→将棊島粗朶水制跡碑→淀川三十石船舟歌碑→天満の子守歌碑→天満青物市場碑→フジハラビル天満堀川跡→吹小屋町筋→蔵のまち天満・菅原町→難波橋→中之島公園→ばらぞの橋→ラジオ塔→天神橋→渡辺津→八軒家浜→天満橋
いつもの私のパターン、古地図と、現在の地図と照らし合わせ、今と昔をイメージして歩いて好評を頂いています。
写真は某カルチャーで2年目で14回目となっていますが、何と女性ばかりの9人の受講生、若い人も多く歴史講座にも関わらず女性に人気があります。
案内は多いグループは35名から最小9名の講座です。
沖本会からシニアの定期講座、カルチャー等の定期講座から単発までにぎやかです。
2023年04月25日
「最古の堀川、東横堀川を見聞する」
今回は堀川の上は阪神高速が通っているが何とか残った東横堀川を案内しました。北浜から東横堀川を下って農人橋までの行程です。
東横堀川は秀吉が大坂城の惣構として最古の堀川です。
そのため、秀吉の遺構が色濃く残っています。

 古地図は今も使えます
古地図は今も使えます



創業百年以上のゼー六で熱いの、冷たいのを頂く

私ツァーでは人気のランチ
東横堀川は秀吉が大坂城の惣構として最古の堀川です。
そのため、秀吉の遺構が色濃く残っています。
今橋の由来を解説
西町奉行所跡
創業百年以上のゼー六で熱いの、冷たいのを頂く
私ツァーでは人気のランチ
2023年03月22日
世界遺産「百舌鳥古墳群と絶品自然食ランチツァー」
桜が開花した、春らしいさなか、枚方にあるカルチャーで昨年から実施しています、「おとなの遠足 世界遺産「百舌鳥古墳群と絶品自然食ランチツァー」を実施しました。
JR百舌鳥に集合し伝仁徳天皇御陵をはじめ9箇所の世界遺産をガイドして一同新たな発見をしていただきました。
その後、野菜料理を懲りに凝った料理を提供する知る人ぞ知る名店、菜食和合茶倉でいただきました。このお店はパット見、住宅地にある戦前の民家でまさか高級料理屋とは分かりません。
予約のみの営業で真の隠れ家といえます。
2時間、ゆったりとした食事と会話を楽しんでいただきました。









JR百舌鳥に集合し伝仁徳天皇御陵をはじめ9箇所の世界遺産をガイドして一同新たな発見をしていただきました。
その後、野菜料理を懲りに凝った料理を提供する知る人ぞ知る名店、菜食和合茶倉でいただきました。このお店はパット見、住宅地にある戦前の民家でまさか高級料理屋とは分かりません。
予約のみの営業で真の隠れ家といえます。
2時間、ゆったりとした食事と会話を楽しんでいただきました。









2023年02月04日
ワンコイン(500円)で~知っているようで知らないおもしろ大阪学「掘って埋めての大阪」
公益社団法人 アジア協会アジア友の会 (JAFS)
(貧困に苦しむアジアの村へ安全な水(井戸)を贈ることを通じ、生活、教育、環境面での支援活動を行っているNGOです。)
私はこの団体活動に共鳴し、募金集めとして15年ほど前から歴史街歩き、講演等のボランティア活動をしています。
今回も、あまり語られていない大阪の良さを分かり易く、興味の持てる切り口で解説します。
もしお時間が許せば是非参加してください。
ワンコイン(500円)で「皆が驚く初耳学」~知っているようで知らない「おもしろ大阪学」として
2月28日(火) おもしろ大阪学 その1
=古代のスーパースター、仁徳天皇、和気清麿=
16:00~17:00 大阪平野の地理の成り立ちから、変遷を、そして古代三大利水工事について解説します。
3月14日(火) おもしろ大阪学 その2
=土木大好き、秀吉、掘れよ埋めよ江戸時代=
16:00~17:00 近世の土木工事として、秀吉時代から、江戸時代の大和川付け替え、堀川、新田開発までを解説します。
4月11日(火) おもしろ大阪学 その3
=土地を増せよ、増せよの近代=
16:00~17:00 近代の土木工事として、淀川改修から受難の川として失われていった堀川、その原因を解説。さらに湾岸部の変化とともに現代の埋立て状態を解説します。
参加費:500円 要予約 場所:JAFS 5階 会議室 参加人数:15名(先着順)
大阪市西区江戸堀1-2-14肥後橋官報ビル5階(大阪メトロ四ツ橋線 四ツ橋すぐ)
TEL 06-6444-0587 FAX 06-6444-0581
Mail:taniguchi@jafs.or.jp
プログラムマネジャー 鳥居京子
なお、JAFSのホームページ イベント欄にも記載されています。
(貧困に苦しむアジアの村へ安全な水(井戸)を贈ることを通じ、生活、教育、環境面での支援活動を行っているNGOです。)
私はこの団体活動に共鳴し、募金集めとして15年ほど前から歴史街歩き、講演等のボランティア活動をしています。
今回も、あまり語られていない大阪の良さを分かり易く、興味の持てる切り口で解説します。
もしお時間が許せば是非参加してください。
ワンコイン(500円)で「皆が驚く初耳学」~知っているようで知らない「おもしろ大阪学」として
2月28日(火) おもしろ大阪学 その1
=古代のスーパースター、仁徳天皇、和気清麿=
16:00~17:00 大阪平野の地理の成り立ちから、変遷を、そして古代三大利水工事について解説します。
3月14日(火) おもしろ大阪学 その2
=土木大好き、秀吉、掘れよ埋めよ江戸時代=
16:00~17:00 近世の土木工事として、秀吉時代から、江戸時代の大和川付け替え、堀川、新田開発までを解説します。
4月11日(火) おもしろ大阪学 その3
=土地を増せよ、増せよの近代=
16:00~17:00 近代の土木工事として、淀川改修から受難の川として失われていった堀川、その原因を解説。さらに湾岸部の変化とともに現代の埋立て状態を解説します。
参加費:500円 要予約 場所:JAFS 5階 会議室 参加人数:15名(先着順)
大阪市西区江戸堀1-2-14肥後橋官報ビル5階(大阪メトロ四ツ橋線 四ツ橋すぐ)
TEL 06-6444-0587 FAX 06-6444-0581
Mail:taniguchi@jafs.or.jp
プログラムマネジャー 鳥居京子
なお、JAFSのホームページ イベント欄にも記載されています。

2022年08月31日
チャリティウォーク for (公財)アジア協会友の会
まいど!大阪おもしろツアー「歴史と文化の天王寺七坂巡り 南エリア」
~チャリティウォーク for (公財)アジア協会友の会
南エリア 夕陽ヶ丘から天王寺へ
知っているようで知らない大阪を、大阪歴史案内人沖本さんに案内いただく、大好評のチャリティまち歩きです。
大阪の聖地・上町台地。約200もの寺社仏閣が集積する、我が国でも有数の一大宗教スポットで、いくつものドラマ、物語が秘められたエリアです。口縄坂、愛染坂、清水坂、天神坂、逢坂を経て天王寺へ。大阪では珍しい木々が茂り、ゆったりとした時間が流れ、歴史と文化の街を巡ります。
主なコース
太平寺→口縄坂→家隆塚→愛染堂→大江神社→愛染坂→清水寺→清水坂→天神坂→安井神社→逢坂→ 一心寺→河底池→大阪市立美術館→てんしば→天王寺
日 時:2022年9月24日(土)10:00~13:00頃
集 合:大阪メトロ谷町線「四天王寺夕陽丘」②番出口(地上部)
会 費:1,000円(会費の一部をインド児童の教育支援に役立てます)
定 員:30名(先着順)
案 内:大阪歴史案内人 沖本然生
*解散:13時頃 天王寺
*終了後、希望者のみランチ会予定
*交通費は各自ご負担下さい。
※新型コロナウィルスの状況、悪天候等により中止する場合がありますので、事前ご了解をお願いします。
申込み・問合せ
JAFSなにわ西地区世話人
風早:tel 090-3944-1582、mail bfaov103@cwo.zaq.ne.jp
伊藤:tel 090-2410-5529、mail ito.masaru320@gmail.com
JAFSのhpは
https://jafs.or.jp/news/eventinfo/20220809.html

~チャリティウォーク for (公財)アジア協会友の会
南エリア 夕陽ヶ丘から天王寺へ
知っているようで知らない大阪を、大阪歴史案内人沖本さんに案内いただく、大好評のチャリティまち歩きです。
大阪の聖地・上町台地。約200もの寺社仏閣が集積する、我が国でも有数の一大宗教スポットで、いくつものドラマ、物語が秘められたエリアです。口縄坂、愛染坂、清水坂、天神坂、逢坂を経て天王寺へ。大阪では珍しい木々が茂り、ゆったりとした時間が流れ、歴史と文化の街を巡ります。
主なコース
太平寺→口縄坂→家隆塚→愛染堂→大江神社→愛染坂→清水寺→清水坂→天神坂→安井神社→逢坂→ 一心寺→河底池→大阪市立美術館→てんしば→天王寺
日 時:2022年9月24日(土)10:00~13:00頃
集 合:大阪メトロ谷町線「四天王寺夕陽丘」②番出口(地上部)
会 費:1,000円(会費の一部をインド児童の教育支援に役立てます)
定 員:30名(先着順)
案 内:大阪歴史案内人 沖本然生
*解散:13時頃 天王寺
*終了後、希望者のみランチ会予定
*交通費は各自ご負担下さい。
※新型コロナウィルスの状況、悪天候等により中止する場合がありますので、事前ご了解をお願いします。
申込み・問合せ
JAFSなにわ西地区世話人
風早:tel 090-3944-1582、mail bfaov103@cwo.zaq.ne.jp
伊藤:tel 090-2410-5529、mail ito.masaru320@gmail.com
JAFSのhpは
https://jafs.or.jp/news/eventinfo/20220809.html


2022年08月13日
講演会「掘って埋めての大阪」その1
真夏はとても日中、外を歩くというのはやる方も、やられる方もたまりません。私は各講座の8月は室内で実施することにしています。
講座内容はというと「知っているようで知らないシリーズ」で、歴史、文化をあまり人がやらない、切口、見方でもって、聞きに来られる方が楽しく興味が湧くようにとを第一にか心がけています。主な講演テーマは「大阪の地名由来」「大阪の難読地名と地名の謎」「大阪の地理」「掘って埋めての大阪」「大阪の謎」シリーズ、「浪華名所獨案内をはじめ古地図を読み解く」シリーズ等々色々と実施。
今回は「掘って埋めての大阪」で大阪の地層は洪積台地の上に積もった沖積土でできています。そのため古墳時代、古代、中世、近世、近代そして現在、未来にわたって、掘って埋めての歴史です。この時代ごとの痕跡を図からも分かり易く、かつ興味が持てる内容で解説しました。
この時期、50人近く集まっていただきうれしい限りです。皆さん満足して頂けたと思います。
これで講演会も無事、4回終え、来週にあるカルチャーセンターでの講演で真夏の行事が終わりますが、秋からの、街歩き講座が待ちかねています。


講座内容はというと「知っているようで知らないシリーズ」で、歴史、文化をあまり人がやらない、切口、見方でもって、聞きに来られる方が楽しく興味が湧くようにとを第一にか心がけています。主な講演テーマは「大阪の地名由来」「大阪の難読地名と地名の謎」「大阪の地理」「掘って埋めての大阪」「大阪の謎」シリーズ、「浪華名所獨案内をはじめ古地図を読み解く」シリーズ等々色々と実施。
今回は「掘って埋めての大阪」で大阪の地層は洪積台地の上に積もった沖積土でできています。そのため古墳時代、古代、中世、近世、近代そして現在、未来にわたって、掘って埋めての歴史です。この時代ごとの痕跡を図からも分かり易く、かつ興味が持てる内容で解説しました。
この時期、50人近く集まっていただきうれしい限りです。皆さん満足して頂けたと思います。
これで講演会も無事、4回終え、来週にあるカルチャーセンターでの講演で真夏の行事が終わりますが、秋からの、街歩き講座が待ちかねています。


2022年08月12日
「謎の鳥居」大阪の歴史と文化
道を歩いていたら突然鳥居が。普通であればここは神社かなと思いますね。それが都会のど真ん中、オフィス街にあるビルの玄関に、それもビルの敷地ではなく道路上に。こんな景色を想像されたことがありますでしょうか。これがなんと大阪の街にはあるんです。
その場所はというと本町の(大阪市中央区淡路町4丁目4−15)「中井エンジニアリング」本社ビル前です。
なぜそんなところに鳥居があるのか、その理由は、中井ビルの北側に鎮座している御霊神社が関係しています。江戸時代までは神社とともに「寶城寺(宝城寺)」と言われる神宮寺が併設されていました。明治時代の神仏分離令により、そのお寺の敷地が国に没収されたことから始まります。その際、鳥居はここにお寺があり、神社の参道だったことを残すために氏子達が立てたのです。お寺はなくなりましたが時は流れ中井エンジニアリングのビルがお寺の敷地に建ったのです。その際、鳥居だけが現在まで残ったというわけです。以前社長の運転手と話をしたさい、狭い鳥居の間から出入りするので非常に気を遣うとのこと。そりゃ鳥居に当てて折れたりしたら大変。私には無理です。
なお、中井エンジニアリングは大阪ガスのトップ工事屋で、「ガンコ石橋店」は中井氏の自宅です。このように大阪には??と思われる意味不明のものがあちらこちらに転がっていて、それを訪ね、空想するのも楽しいものです。
御霊神社は津布良彦神 (旧攝津国津村郷の産土神)つぶらしんで明治17年(1884年)、人形浄瑠璃の劇場「文楽座」が境内に開設。「御霊文楽座」として、文楽二百年の歴史のうちでも、近世文楽における黄金期のにぎわいを見せ〝御霊文楽″の名で親しまれ、「文楽といえば御霊」といわれるほどの盛況を博していました。そのため神社周辺には御霊文楽の観客を目当てに料亭の「魚禰」や天ぶらの「天真」、どじょうの「美濃庄」、うどんの「美々卯」などの店が軒を並べ、大阪人の娯楽と社交の場となっていました。現在も「美々卯」本店が残ります。
ただ、2022年5月5日現在、中井本社ビル立て替えのため鳥居を含め工事幕が張られ全体が見ることができません。完成した暁には元の異様な風景が戻ることを願います。


その場所はというと本町の(大阪市中央区淡路町4丁目4−15)「中井エンジニアリング」本社ビル前です。
なぜそんなところに鳥居があるのか、その理由は、中井ビルの北側に鎮座している御霊神社が関係しています。江戸時代までは神社とともに「寶城寺(宝城寺)」と言われる神宮寺が併設されていました。明治時代の神仏分離令により、そのお寺の敷地が国に没収されたことから始まります。その際、鳥居はここにお寺があり、神社の参道だったことを残すために氏子達が立てたのです。お寺はなくなりましたが時は流れ中井エンジニアリングのビルがお寺の敷地に建ったのです。その際、鳥居だけが現在まで残ったというわけです。以前社長の運転手と話をしたさい、狭い鳥居の間から出入りするので非常に気を遣うとのこと。そりゃ鳥居に当てて折れたりしたら大変。私には無理です。
なお、中井エンジニアリングは大阪ガスのトップ工事屋で、「ガンコ石橋店」は中井氏の自宅です。このように大阪には??と思われる意味不明のものがあちらこちらに転がっていて、それを訪ね、空想するのも楽しいものです。
御霊神社は津布良彦神 (旧攝津国津村郷の産土神)つぶらしんで明治17年(1884年)、人形浄瑠璃の劇場「文楽座」が境内に開設。「御霊文楽座」として、文楽二百年の歴史のうちでも、近世文楽における黄金期のにぎわいを見せ〝御霊文楽″の名で親しまれ、「文楽といえば御霊」といわれるほどの盛況を博していました。そのため神社周辺には御霊文楽の観客を目当てに料亭の「魚禰」や天ぶらの「天真」、どじょうの「美濃庄」、うどんの「美々卯」などの店が軒を並べ、大阪人の娯楽と社交の場となっていました。現在も「美々卯」本店が残ります。
ただ、2022年5月5日現在、中井本社ビル立て替えのため鳥居を含め工事幕が張られ全体が見ることができません。完成した暁には元の異様な風景が戻ることを願います。


2022年07月19日
「乳牛牧跡(ちゅうしまきあと)」大阪の歴史・文化
なんと東淀川区に、古代の牧場があったのです。
「日本書紀』535年の9月に、安閑天皇により「牛を難波大隅嶋と媛嶋松原に放て」という記事が見て取れます。古代律令制時代以来、典薬寮(てんやくりょう:朝廷で医薬を取り扱っていた官省)に所属していた牛牧「味原牧(あじふのまき)」がありました。「味原牧」は、摂津市の味原(あじふ)の地から淀川が分流する江口の下流部(現在の南江口・大桐・大道南あたり)に分布していたといわれ、乳牛を飼育していたことから「乳牛牧」と呼ばれていました。なお、姫嶋松原は今の西淀川区姫島あたりで、ここが古代から陸地だったことが分かります。中世には乳牛牧荘とも呼ばれる酪農の拠点になりました。牛牧の住民は牛を飼育して、牛乳や蘇(そ:牛乳を煮つめて濃くしたもの)、酪(らく:牛乳を精煉した飲料、それから作るチーズなど)を製造するとともに、毎年、母牛と子牛を典薬寮の乳牛院に送ることが義務づけられていました。「延喜式」にも大隅嶋牧、姫嶋牧から1日3升1合5勺を調達し納め天皇・皇后をはじめ宮廷で飲用された、とあります。現在の大隅東・西小学校は、大正15年(1926年)に改称する以前は「乳牛牧尋常小学校」と称していましたし、乳牛牧村もあり歴史にその名を残していたことが分かります。
醍醐(だいご)とは、五味の最高に精製された牛乳の加工品で、濃厚な味わいとほのかな甘味を持った液汁とされ、最も美味しい蘇は醍醐味といわれています。今も奈良の明日香に行けば食べられます。飽食の時代の現代人、さて醍醐味となるかは食した人次第。天皇・皇后しか食されなかったものがワンコインで食べれますよ。
またネットではコロナ禍による「牛乳」が余るということで牛乳を大量消費できる「蘇」レシピが話題になっていますね。方法は簡単ですが長時間の根気が必要なようです。
ちなみに史料による初めて牛乳を愛飲された天皇は、難波宮におられた孝徳天皇といわれています。
「延喜式」に善和使王が牛乳を献じたので和薬使王(やまとのくすりのおみ)の称号を賜わるとあるのが分かる。善和使王はここ大隅嶋牧、姫嶋牧から1日3升1合5勺を調達し納めた。天皇・皇后をはじめ宮廷で飲用されたとある。このように柴島の地は古代から開かれた地と言える。事実、この地は大阪でも高台であったと言える。もともと大阪は淀川、大和川のが運んできた土が堆積してできた土地で沖積土でできている。そのためほとんど海抜0m地域がおおい。この地は古代より周囲より高地であったといえる。そのため明治28年11月に「桜の宮水源地」が創設され、水道事業がはじまりましたが、その後の水道事業拡張により、数カ所の案のなかから幾多の曲折を経た後、柴島に水源地の建設が計画されました。そして、当時東洋一といわれた「柴島水源地」が大正3年3月に完成その際、候補に挙がったのがここ、大隅の土地です。なぜ高地である必要が、まず流すのに有利、また水害の時水没しにくいなどの理由によります。このように淀川右岸の江口から柴島は古代より微高地だったといえます。


「日本書紀』535年の9月に、安閑天皇により「牛を難波大隅嶋と媛嶋松原に放て」という記事が見て取れます。古代律令制時代以来、典薬寮(てんやくりょう:朝廷で医薬を取り扱っていた官省)に所属していた牛牧「味原牧(あじふのまき)」がありました。「味原牧」は、摂津市の味原(あじふ)の地から淀川が分流する江口の下流部(現在の南江口・大桐・大道南あたり)に分布していたといわれ、乳牛を飼育していたことから「乳牛牧」と呼ばれていました。なお、姫嶋松原は今の西淀川区姫島あたりで、ここが古代から陸地だったことが分かります。中世には乳牛牧荘とも呼ばれる酪農の拠点になりました。牛牧の住民は牛を飼育して、牛乳や蘇(そ:牛乳を煮つめて濃くしたもの)、酪(らく:牛乳を精煉した飲料、それから作るチーズなど)を製造するとともに、毎年、母牛と子牛を典薬寮の乳牛院に送ることが義務づけられていました。「延喜式」にも大隅嶋牧、姫嶋牧から1日3升1合5勺を調達し納め天皇・皇后をはじめ宮廷で飲用された、とあります。現在の大隅東・西小学校は、大正15年(1926年)に改称する以前は「乳牛牧尋常小学校」と称していましたし、乳牛牧村もあり歴史にその名を残していたことが分かります。
醍醐(だいご)とは、五味の最高に精製された牛乳の加工品で、濃厚な味わいとほのかな甘味を持った液汁とされ、最も美味しい蘇は醍醐味といわれています。今も奈良の明日香に行けば食べられます。飽食の時代の現代人、さて醍醐味となるかは食した人次第。天皇・皇后しか食されなかったものがワンコインで食べれますよ。
またネットではコロナ禍による「牛乳」が余るということで牛乳を大量消費できる「蘇」レシピが話題になっていますね。方法は簡単ですが長時間の根気が必要なようです。
ちなみに史料による初めて牛乳を愛飲された天皇は、難波宮におられた孝徳天皇といわれています。
「延喜式」に善和使王が牛乳を献じたので和薬使王(やまとのくすりのおみ)の称号を賜わるとあるのが分かる。善和使王はここ大隅嶋牧、姫嶋牧から1日3升1合5勺を調達し納めた。天皇・皇后をはじめ宮廷で飲用されたとある。このように柴島の地は古代から開かれた地と言える。事実、この地は大阪でも高台であったと言える。もともと大阪は淀川、大和川のが運んできた土が堆積してできた土地で沖積土でできている。そのためほとんど海抜0m地域がおおい。この地は古代より周囲より高地であったといえる。そのため明治28年11月に「桜の宮水源地」が創設され、水道事業がはじまりましたが、その後の水道事業拡張により、数カ所の案のなかから幾多の曲折を経た後、柴島に水源地の建設が計画されました。そして、当時東洋一といわれた「柴島水源地」が大正3年3月に完成その際、候補に挙がったのがここ、大隅の土地です。なぜ高地である必要が、まず流すのに有利、また水害の時水没しにくいなどの理由によります。このように淀川右岸の江口から柴島は古代より微高地だったといえます。

2022年06月14日
「大阪の百済」 大阪の歴史と文化
知っているようで知らない大阪 大阪の歴史・文化
「大阪の百済」
大阪に百済が??、百済って、古代朝鮮の国名ではと疑問に思われる方も多いと思いますが事実なのです。その痕跡は今も残っていますよ。
古代朝鮮は北から高句麗、新羅、百済と三つの国から成り立っていました。ヤマト朝廷は4世紀後半にほぼ日本列島を統一し、同時に朝鮮半島、特に南に位置する百済との交流が始まりました。資料に残るのは369年ころ百済と国交樹立をすることとなります。そのことが石上神宮所蔵「七支刀」(国宝)銘文に書かれています。応神朝の時代に難波大隅の宮(現在の東淀川区)があったとされます。その後、百済の聖明王から金銅像、経本などが欽明13年(552)送られると、『日本書紀』に記述が残っています。善光と豊璋の2人の皇太子が舒明天皇3年(631年)に来日。ところが、660年には百済は唐や新羅に攻められ滅亡し、その後、663年白村江の戦いで完敗する。それゆえに大勢の人が日本へ渡来し、残された善光をはじめ百済王一族が難波(天王寺区堂ケ芝・百済寺跡と細工谷・百済尼寺跡)に居住したことが、「日本書紀」天智3年条に “百済王善(禅)光王以て難波に居べらしむ”と記されています。その最初の居住地が今の天王寺の東部であり、この一帯に、百済郡ができたと考えられます。『続日本紀』によれば、聖武天皇が大仏に鍍金するための黄金探索をしていたところ、当時陸奥国で金を発見され天皇は狂喜し異例の7階級特進の大出世をした百済王敬福は、天平勝宝2年(750年)に河内守を命じられたという。これを契機として、一族の本拠を河内国へと移し百済野は一旦消滅することになります。現在枚方市に史跡として百済寺があるのはそのためです。
時は飛んで1100年経た明治22年(1889年)に鷹合、砂子、湯谷島、中野の4ケ村が合併して、南百済村、北百済村は桑津、今林、杭全、今川が合併されたことに因みます。ただ1925年(大正14年)の大阪市二次市域拡張により消滅することに。現在は南百済小学校や百済公園に百済大橋などにその地名が残るのみで、行政上での地名はなくなっています。JR東部市場前駅周辺は、明治42年(1909)から昭和20年(1945)ころまでは近くに旧国鉄の旅客駅「百済駅」も存在していました。今は貨物駅として存在しています。このように生野から東住吉区にかけて古代から多くの渡来人が生活していました。勿論百済以外、新羅も高麗も勿論痕跡が多く残ります。ちなみに平野川は百済川、駒川は高麗川と書かれていたことがわかっています。


「大阪の百済」
大阪に百済が??、百済って、古代朝鮮の国名ではと疑問に思われる方も多いと思いますが事実なのです。その痕跡は今も残っていますよ。
古代朝鮮は北から高句麗、新羅、百済と三つの国から成り立っていました。ヤマト朝廷は4世紀後半にほぼ日本列島を統一し、同時に朝鮮半島、特に南に位置する百済との交流が始まりました。資料に残るのは369年ころ百済と国交樹立をすることとなります。そのことが石上神宮所蔵「七支刀」(国宝)銘文に書かれています。応神朝の時代に難波大隅の宮(現在の東淀川区)があったとされます。その後、百済の聖明王から金銅像、経本などが欽明13年(552)送られると、『日本書紀』に記述が残っています。善光と豊璋の2人の皇太子が舒明天皇3年(631年)に来日。ところが、660年には百済は唐や新羅に攻められ滅亡し、その後、663年白村江の戦いで完敗する。それゆえに大勢の人が日本へ渡来し、残された善光をはじめ百済王一族が難波(天王寺区堂ケ芝・百済寺跡と細工谷・百済尼寺跡)に居住したことが、「日本書紀」天智3年条に “百済王善(禅)光王以て難波に居べらしむ”と記されています。その最初の居住地が今の天王寺の東部であり、この一帯に、百済郡ができたと考えられます。『続日本紀』によれば、聖武天皇が大仏に鍍金するための黄金探索をしていたところ、当時陸奥国で金を発見され天皇は狂喜し異例の7階級特進の大出世をした百済王敬福は、天平勝宝2年(750年)に河内守を命じられたという。これを契機として、一族の本拠を河内国へと移し百済野は一旦消滅することになります。現在枚方市に史跡として百済寺があるのはそのためです。
時は飛んで1100年経た明治22年(1889年)に鷹合、砂子、湯谷島、中野の4ケ村が合併して、南百済村、北百済村は桑津、今林、杭全、今川が合併されたことに因みます。ただ1925年(大正14年)の大阪市二次市域拡張により消滅することに。現在は南百済小学校や百済公園に百済大橋などにその地名が残るのみで、行政上での地名はなくなっています。JR東部市場前駅周辺は、明治42年(1909)から昭和20年(1945)ころまでは近くに旧国鉄の旅客駅「百済駅」も存在していました。今は貨物駅として存在しています。このように生野から東住吉区にかけて古代から多くの渡来人が生活していました。勿論百済以外、新羅も高麗も勿論痕跡が多く残ります。ちなみに平野川は百済川、駒川は高麗川と書かれていたことがわかっています。


 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン